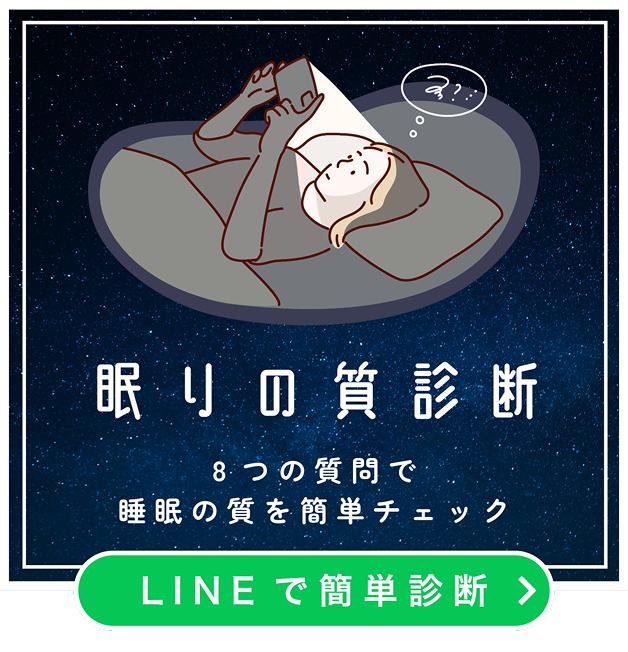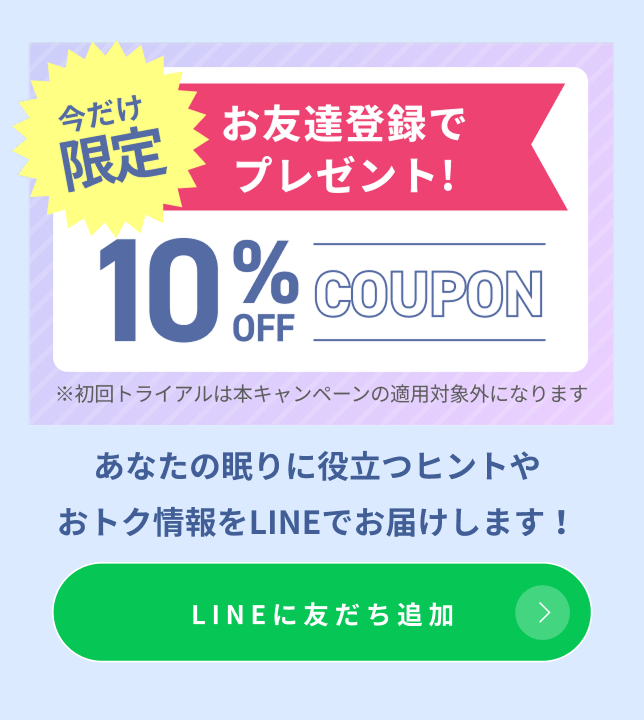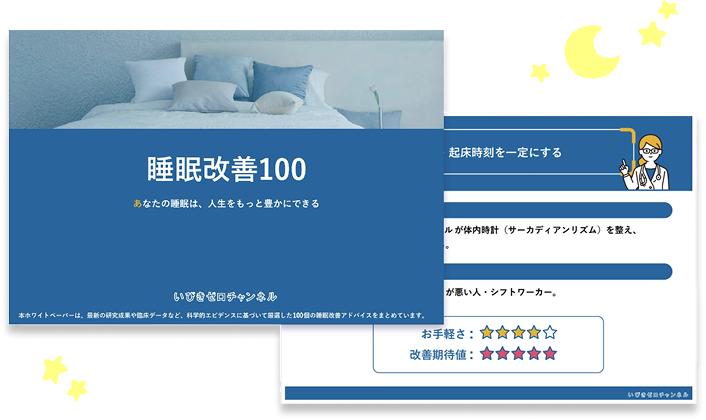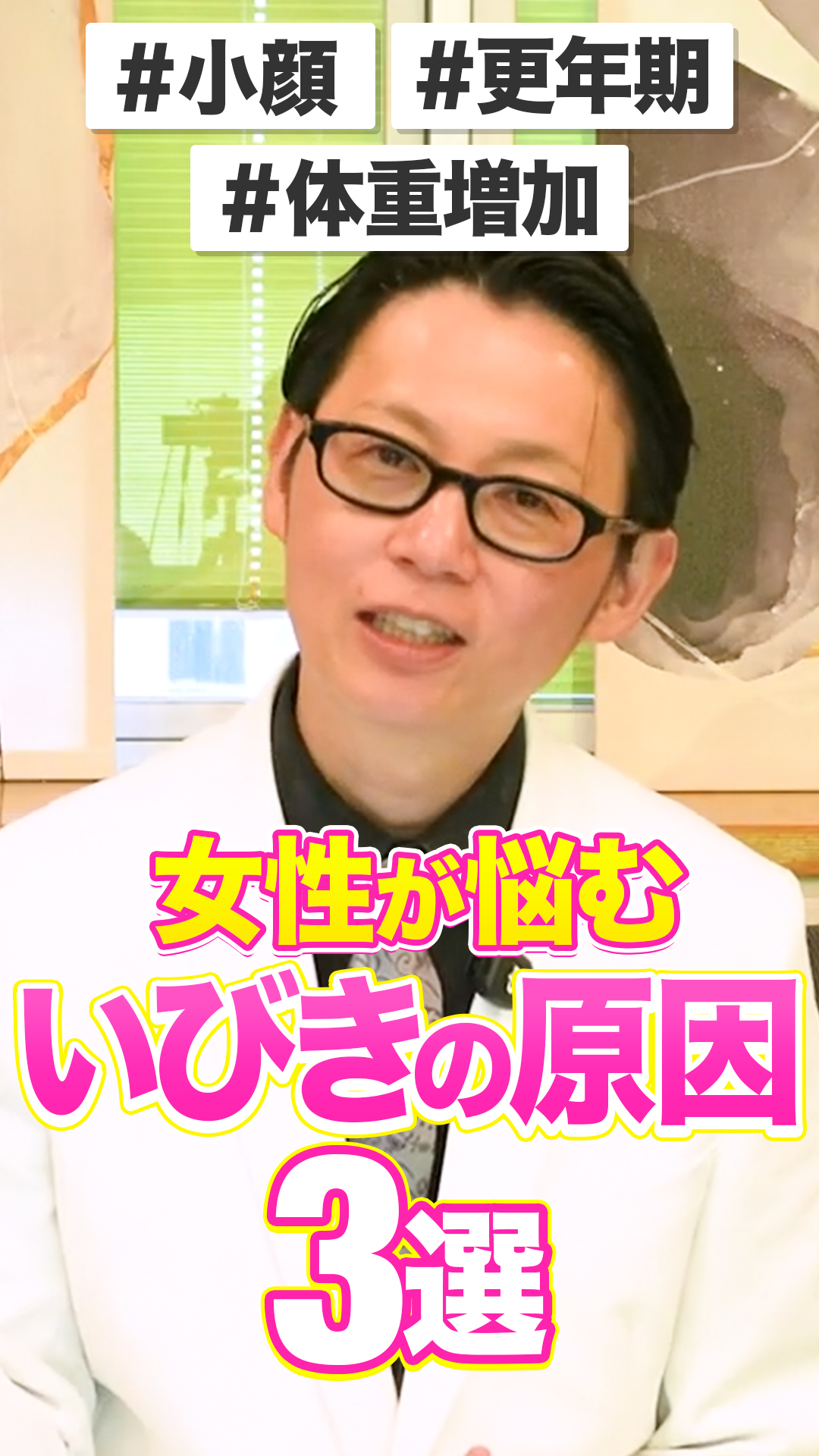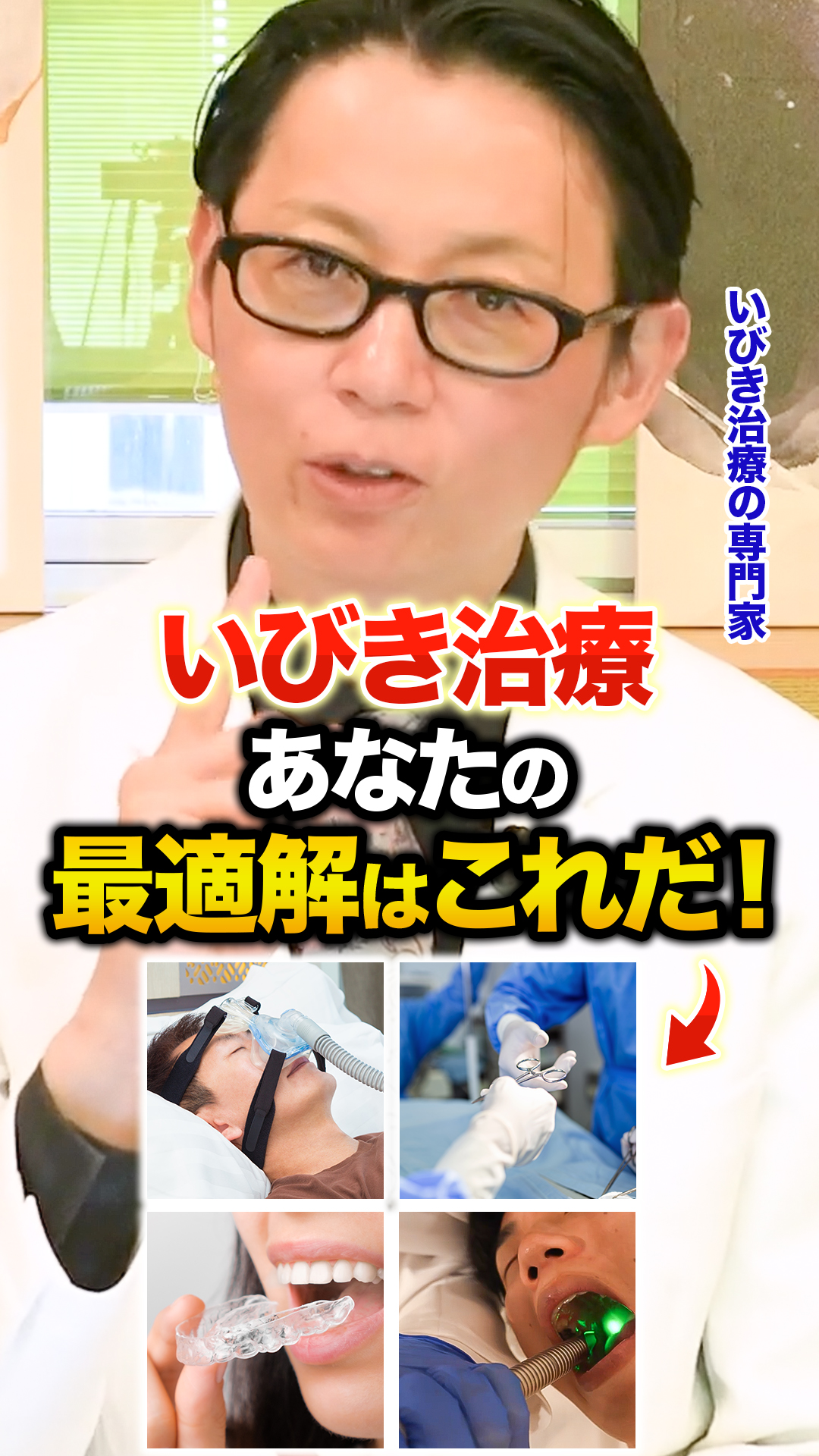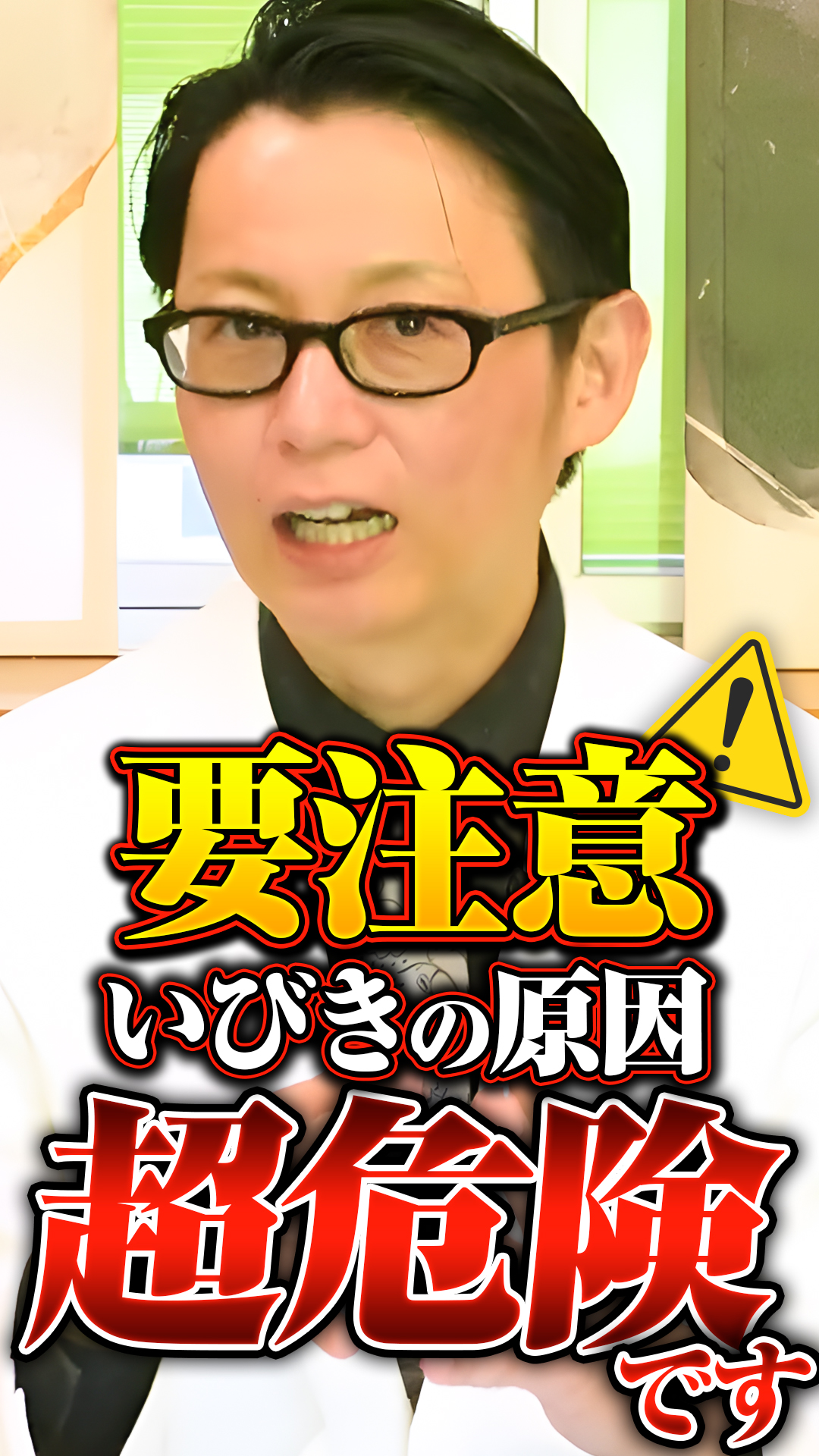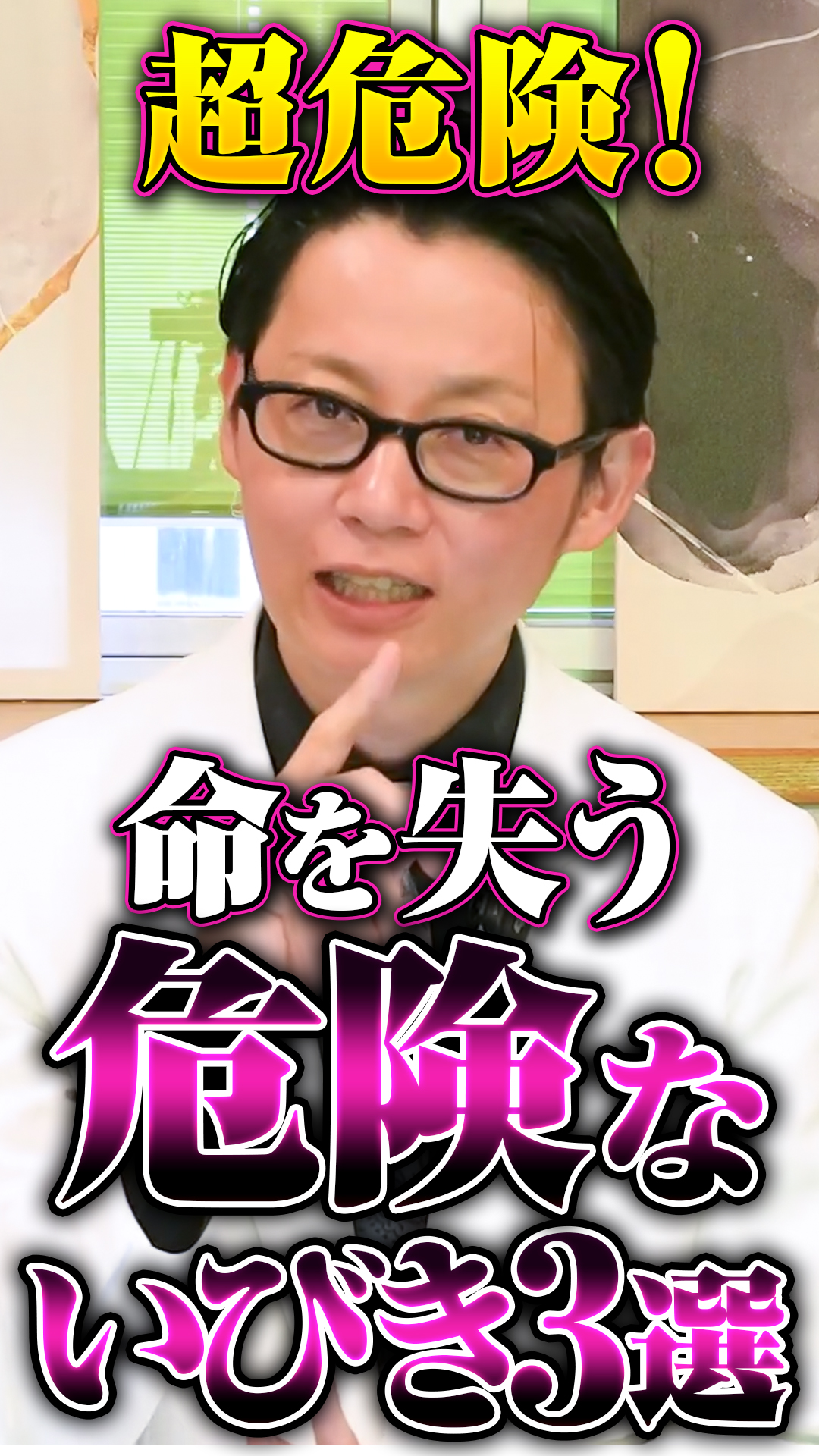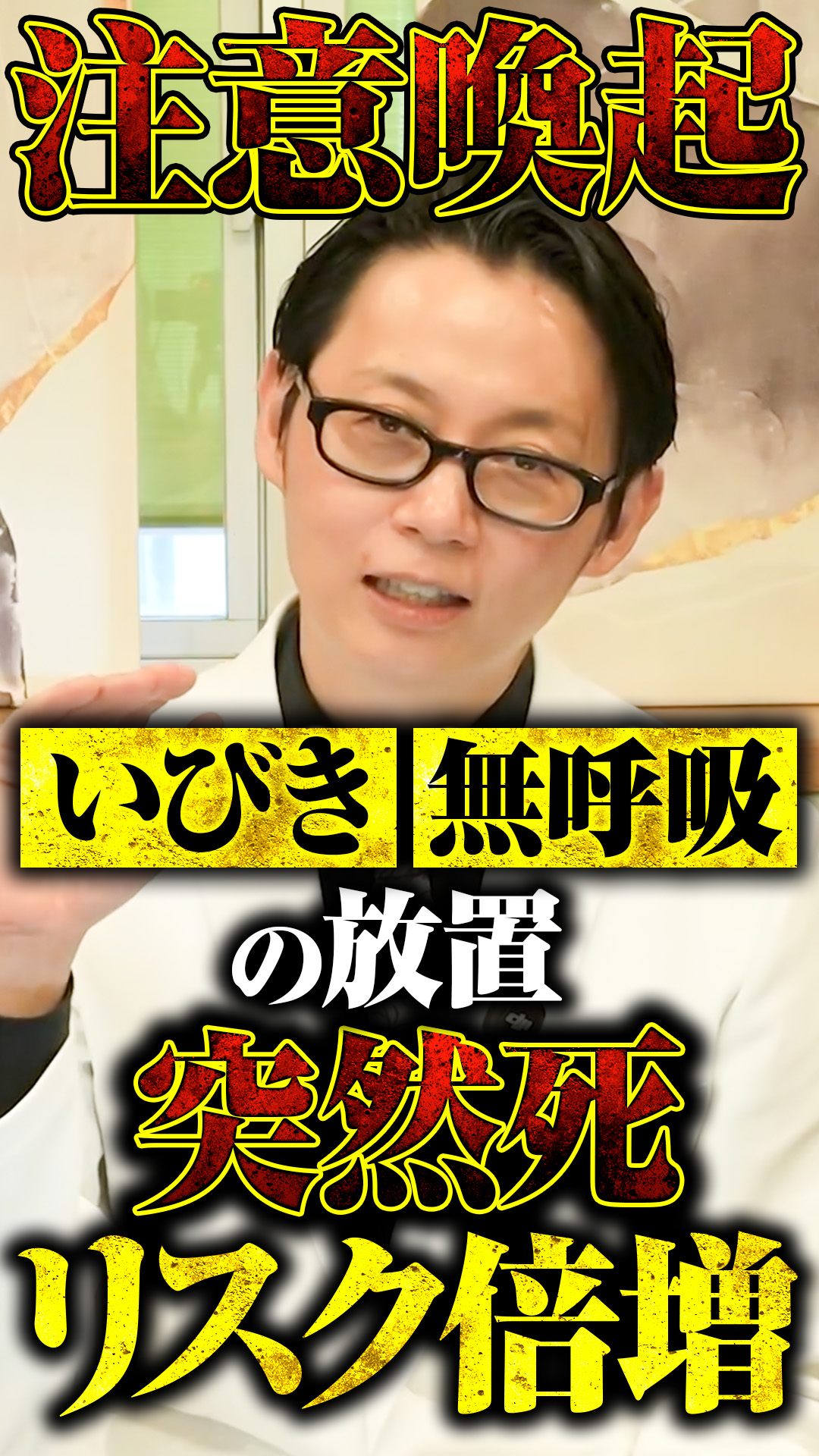痩せ型無呼吸症候群のリスクとは?専門家が答える症状・治療完全ガイド
睡眠時無呼吸症候群の方々にとって、自身の健康リスクを正しく理解することは非常に重要です。一般的には肥満が大きな発症リスクとされますが、実は痩せ型の方でも無呼吸症候群にかかる可能性があり、その特徴やリスクは異なる場合が多くあります。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一時的に止まることで、日中の強い眠気や集中力低下を引き起こすだけでなく、心血管系の疾患リスクも高まる深刻な睡眠障害です。特に痩せ型の患者様には見過ごされがちな症状や、目立たないリスク因子が存在するため、早期の理解と対策が欠かせません。
こうした痩せ型無呼吸症候群のリスクや異なる症状の見分け方、そして顎の骨格や気道構造との関連性について深く掘り下げながら、専門的な知見をもとにわかりやすく解説します。さらに、痩せ型の患者様に適した治療法や日常生活で取り入れたい予防策まで、幅広くご紹介していきます。
痩せ型無呼吸症候群とは?
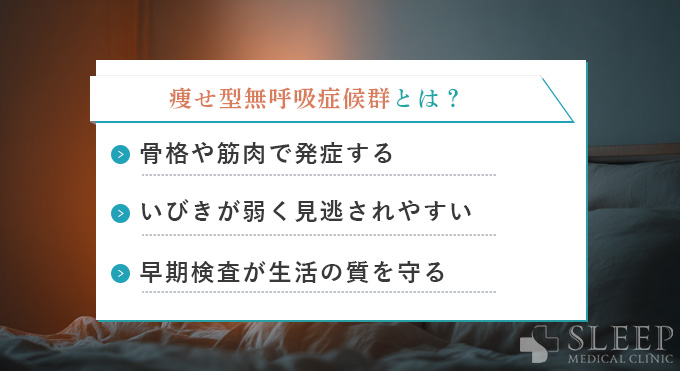
痩せ型の方に特有の無呼吸症候群の特徴を詳述します。さらに、痩せ型で見逃されやすい症状にも注意を喚起し、早期発見のヒントをお伝えします。
痩せ型における無呼吸症候群の特徴
痩せ型の方における睡眠時無呼吸症候群は、肥満型の方とは異なるメカニズムと特徴を持っています。一般的に肥満型では、首周りの脂肪組織が増加し、気道を圧迫することが主な原因ですが、痩せ型の場合は骨格構造や筋肉の萎縮、内臓脂肪の配置などが影響するとされています。
痩せ型の患者様には、特に顎の骨格異常や小顎症といった構造的な気道狭窄、または舌根沈下が起こりやすい点が指摘されています。こうした骨格の問題は、空気の通り道を狭め、閉塞リスクを高めるため、肥満がなくても無呼吸を引き起こし得るのです。
また、痩せ型の方は筋肉量が少ない傾向があるため、睡眠中の喉周囲筋肉の緊張低下が気道閉塞につながる場合もあります。これにより、無呼吸の発生頻度や重症度に差が生じることがあるのが特徴です。
一方で、痩せ型の患者様の内臓脂肪の分布に関連する研究では、皮下脂肪は少なくても内臓脂肪比率が高い場合、気道周辺の脂肪沈着が無呼吸の悪化に関与する可能性が示唆されています。しかし、肥満型と比べると痩せ型はこれらの脂肪蓄積が少ないため、検査や診断の際に見逃されるリスクも伴います。
痩せ型で見落とされやすい症状
痩せ型の無呼吸症候群は診断が遅れやすい傾向にあります。その理由は、一般的な無呼吸症候群のイメージが肥満と強く結び付いているためです。
特に以下の症状は見逃されやすいので注意が必要です。
- いびきが軽度またはない:肥満型に比べていびきが目立たない場合が多く、家族から指摘されにくいことがあります。
- 日中の軽い眠気や疲労感:重度の眠気ではなく、慢性的な疲れとして認識されやすいです。
- 無呼吸発作の自覚がない:寝ている間の呼吸停止に気づかないため、専門医による検査が重要となります。
- 心理的症状や情動の乱れ:睡眠不足や酸素不足が長期化すると、うつ症状やイライラを引き起こすこともあります。
こうした症状は他の病気や生活習慣の影響と間違えられることが多く、医療機関での詳しい問診や睡眠検査(ポリソムノグラフィー)が必要です。
症状に気がついた場合は早めに専門医の受診をおすすめします。適切な診断と治療により、生活の質の向上が期待できます。
なお、「息苦しさを感じて目が覚める」などの症状に心当たりがある方は、「寝ようとすると息が苦しい?睡眠時の呼吸障害の症状と改善法」の記事もあわせてご覧ください。原因や対処法をわかりやすくまとめています。
睡眠時無呼吸症候群とは?
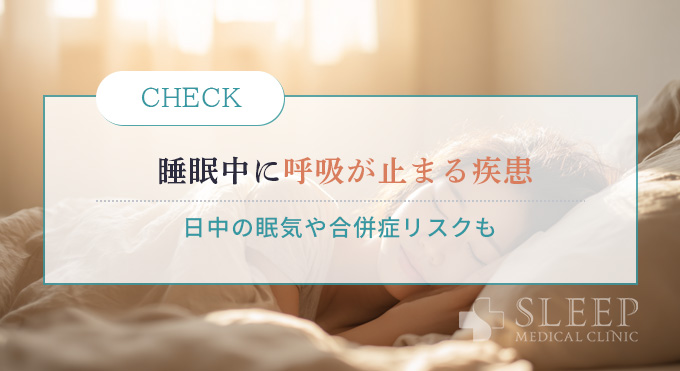
このセクションでは、睡眠時無呼吸症候群の主な症状や初期段階から重症化までのサインを段階的に紹介します。
睡眠時無呼吸症候群の基礎知識
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome、SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に止まるか、浅くなる状態が繰り返される病態です。これは気道の閉塞や狭窄により空気の通り道が確保できず、数秒から数十秒にわたり呼吸が停止する「無呼吸」や、呼吸が極端に浅くなる「低呼吸」が発生することを特徴としています。
この状態が繰り返されると、肺への酸素供給が不十分となり、夜間の睡眠の質が低下、日中の強い眠気や集中力低下、さらに心血管疾患や糖尿病などの合併症リスクが高まることが知られています。
睡眠時無呼吸症候群は大きく分類すると閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)と中枢性睡眠時無呼吸症候群の2つがありますが、一般的に多いのは閉塞性であり、気道が物理的に狭くなることで発症します。
日本睡眠学会などの専門機関によると、成人の数%が何らかの睡眠時無呼吸症候群を持つとされ、その多くが未診断のまま生活していると報告されています。特に、肥満がリスクとしてよく知られているため、痩せ型の場合はリスクを軽視されがちですが、近年では痩せ型でも発症リスクが存在することが注目されています。
なお、睡眠時無呼吸症候群の基本的なメカニズムや症状、治療法についてさらに詳しく知りたい方は、「保存版|睡眠時無呼吸症候群の症状と治療、生活改善のポイント」の記事をご覧ください。初めての方にもわかりやすく、網羅的に解説しています。
睡眠時無呼吸症候群の主な症状とは?
睡眠時無呼吸症候群が疑われる際に、確認すべき主な症状は多岐に渡ります。
- いびき:無呼吸の初期サインとして最も一般的。痩せ型でも強いいびきをかくことがあります。
- 日中の過度な眠気や疲労感:夜間の酸素不足や睡眠の断片化によるものです。集中力や記憶力の低下を来すこともあります。
- 頻繁な夜間覚醒:息苦しさを感じて目が覚めることが多くなります。
- 口の渇きや喉の痛み:口呼吸が増えるため生じやすい症状です。
- 頭痛:特に朝起きたときに感じる頭痛は、低酸素状態の影響と考えられます。
- 高血圧や心臓の不調:無呼吸が重症化すると心血管系に負担がかかります。
これらの症状の進行具合によって、軽度から重度までの分類がされます。軽度の場合は周期的な無呼吸が少ないものの、中等度・重度になると呼吸停止が長時間続くため、合併症のリスクも比例して高まります。
また、痩せ型の患者様はこれらの症状を自己判断しにくく、いびきを伴わない例や軽い日中疲労程度で片付けられることもあるため、早期発見が非常に難しい側面もあります。
とはいえ、「もしかして…」という小さな違和感を見逃さないことが、早期発見への第一歩です。ご自身の状態を把握するために、「睡眠時無呼吸症候群を自分で簡単にセルフチェック!症状や治療法まで徹底解説」の記事をぜひご活用ください。簡単な質問形式で、リスクの有無を確認できます。
顎の骨格と睡眠時無呼吸症候群の関連性
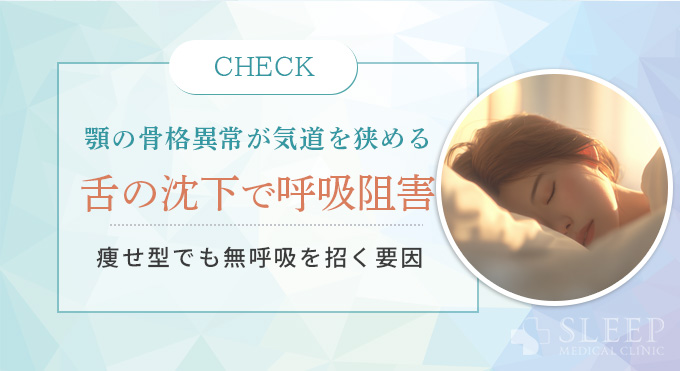
顎の骨格構造は、睡眠時無呼吸症候群の発症に深く関与します。痩せ型の患者様の場合、脂肪組織の蓄積が少ない分、骨格の形態や位置異常が気道閉塞の主な原因となりやすいのです。ここでは、顎変形がどのように気道の狭窄を起こし、無呼吸に繋がるのか、その生理的なメカニズムを詳しく見ていきます。
顎変形による気道狭窄の仕組み
睡眠中、筋肉の弛緩により気道が狭くなりやすいのは誰にでも起こる生理現象ですが、顎の骨格異常があると狭窄が顕著になります。特に下顎の後退(後退顎)や狭小顎は、舌の位置が自然に喉の奥へ沈み込みやすく、気道を圧迫します。
痩せ型の患者様では、顎骨の後方変位など骨格的な狭窄が無呼吸発症の一因として指摘されています。例えば、下顎骨が小さいと舌の収まるスペースが減少し、仰向けで睡眠中に舌根が垂れ下がって気道を塞ぐことが起こります。これが連続的な呼吸停止につながるため、無呼吸症状が出やすくなります。

上顎骨の成長不全による狭い鼻腔や口腔内スペースも、呼吸の妨げとなります。顎骨の位置と形態は顔面の骨格バランスと密接に関係しており、これが乱れると気道の断面積が減少しやすくなります。
痩せ型の患者様に多い骨格異常の具体例
痩せ型無呼吸症候群の患者様でよく見られる骨格異常は、以下のようなものがあります。
- 下顎後退(マイクログナシア):下顎骨が通常より後ろに位置し、舌の位置が喉側に移動しやすくなる
- 狭窄した上顎アーチ:上顎の幅が狭く、鼻呼吸がしにくくなることが多い
- 開咬や口蓋の形状異常:上下の歯が閉じにくく、舌の動きが制限されやすい
- 顔面高形成:顔が縦長で骨格が細長いタイプが多く、気道が細くなる
これらの骨格異常は単独でも気道狭窄の原因になりますが、痩せ型の方では脂肪組織が少ないために隠れた骨格異常が無呼吸の大きな因子として働くことが多いです。実際に専門クリニックでの検査では、痩せ型の患者様の多くに何らかの顎骨変形が認められるというデータもあります。
例えば、大学病院で診察を受けた30代の女性患者様は、痩せ型で肥満がないにもかかわらず重度の無呼吸が認められました。精密検査の結果、下顎後退と広狭い上顎アーチによる慢性的な気道狭窄が原因と判明し、専門的な骨格矯正治療が検討されました。
また、別の例では40代男性患者様が顎の小ささからくる睡眠中の気道閉塞を訴え、下顎前方移動手術を受けて症状が著しく改善したケースもあります。こうした事例は痩せ型特有の顎骨形態が無呼吸の重要なリスクファクターであることを示しています。
顎の骨格と他のリスク因子の複合的影響
顎骨の異常は無呼吸症候群の単独要因にとどまらず、他のリスク因子と複合的に影響し合います。例えば、喉の筋肉の緊張低下、睡眠中の体位、喫煙やアルコール摂取習慣なども、顎の骨格異常の悪化に拍車をかける要因です。
特に痩せ型の場合は、脂肪のクッション効果が少ないことによって、少しの骨格異常でも呼吸路を容易に塞ぐ傾向があります。加えて、加齢によって顔面骨格の変化や筋力低下が進むと、睡眠時の気道閉塞はさらに悪化することがあります。
複合リスクのひとつの例として、顎変形症の存在に加え、睡眠時の体位が仰向けが多い場合、舌根沈下と顎骨位置異常が相乗効果で無呼吸症状を強めることがあります。こうした場合、単なる生活改善だけでは症状の改善が見込めず、専門的な治療が必要になることが明らかです。
痩せ型無呼吸症候群の治療法と対策法

痩せ型無呼吸症候群の治療は、多角的にアプローチすることが効果的です。顎の骨格異常に起因する症例では、機器療法や手術療法に加えて生活習慣の改善も重要です。ここでは診断のポイントから、痩せ型に適した治療法と実際の成功事例、自宅でできる予防や症状緩和法まで分かりやすく解説します。
診断方法と痩せ型特有の検査ポイント
痩せ型の患者様は、肥満型とは異なる検査が必要となる場合が多いです。一見すると外見上のリスクは少なく見えがちですが、顎の骨格や筋肉弛緩の程度を精密に評価することが欠かせません。
主な診断方法としては、以下があります。
- PSG(終夜睡眠ポリグラフ検査):睡眠中の呼吸停止の有無を包括的に測定し、無呼吸指数(AHI)を算出する。
- CTおよびMRI検査:顎の骨格形態、気道断面積の詳細な評価に用いる。
- 内視鏡検査:気道の狭窄状態、舌根の動きや喉の筋肉の収縮具合を直接観察。
- 顎の三次元解析:専門施設で実施され、顎位置や骨格のゆがみを正確に把握できる。
とくに痩せ型の患者様では、顎骨の後退や狭小が深刻な気道閉塞を引き起こしているケースが多く、これらの骨格的検査に重点が置かれます。機械的な検査結果だけでなく、顔面形態の計測や筋肉の緊張度合いも専門医が詳細に評価します。
検査結果に応じて、治療計画を綿密に立てることが無呼吸改善への第一歩となります。
治療法の種類
痩せ型の無呼吸症候群に対しては、それぞれの症状や顎骨形態に合わせた治療法を組み合わせることが推奨されます。
- 持続的陽圧呼吸療法(CPAP):寝ている間に気道に一定の陽圧をかけて閉塞を防ぐ機器療法。痩せ型の患者様でも気道廓開に効果があるが、顎骨の問題が強い場合は補助的に使われることが多い。
- 口腔内装置(OA)療法:下顎を前方に保持するマウスピース型装置で、気道確保に貢献。顎の骨格異常が軽度から中等度の痩せ型の患者様に特に適応されやすい。
- 外科的手術療法:下顎前方移動術、口蓋垂切除術、鼻腔拡大手術など。顎骨の不正が顕著な場合、顎矯正手術が有効。複数の専門科チームでの診断・施術が推奨される。
- 生活習慣の改善:仰向け睡眠の回避や禁煙、就寝前のアルコール制限など。これらは症状の悪化予防に不可欠であると同時に、治療効果の最大化にも寄与する。
また、顎の筋肉を鍛える口腔筋機能療法(MFT)も注目されています。これは舌や咽頭の筋肉トレーニングを行うことで、気道の支持を強化し無呼吸の軽減に寄与する方法です。痩せ型の患者様においては骨格異常による気道狭窄に対抗するため、こうした筋機能治療の併用が効果的となるケースも少なくありません。
痩せ型の患者様に適した治療法と成功例
痩せ型の患者様には、骨格の特性を踏まえたオーダーメイドの治療が求められます。例えば、単にCPAPを装着するだけでは十分な効果が得られない場合が多く、骨格矯正や口腔内装置の併用が望ましいことがあります。
ある20代女性の患者様は、痩せ型でありながら重度の無呼吸を発症。診断で下顎後退が大きな原因であることが判明し、下顎前方移動手術を実施しました。術後は無呼吸指数が劇的に改善し、日中の眠気や集中力低下も解消されました。
別の40代男性の患者様は、顎骨の問題に加えて睡眠中の仰向け寝が無呼吸悪化の誘因となっていました。口腔内装置と体位管理を組み合わせることで、症状が大幅に軽減。手術は回避でき、生活の質が向上しました。
このように、痩せ型の患者様の治療成功には複数の視点からのアプローチが欠かせません。治療方針は、専門の睡眠外来での継続的な評価と調整により最適化されます。
自宅でできる予防と症状緩和法
痩せ型無呼吸症候群の症状軽減には、自宅でのセルフケアも大きな役割を果たします。次のような生活習慣の見直しが効果的です。
- 睡眠姿勢の改善:仰向けを避け、横向きで寝ることで舌根の気道への落ち込みを抑える
- 鼻呼吸の促進:鼻づまり対策や鼻呼吸トレーニングで空気の通り道を確保
- 禁煙・節酒:喉の炎症や筋肉の弛緩を防ぎ、気道の健康維持に寄与
- 適度な運動:全身の筋力・体力アップを通じて、気道周囲の筋肉支持を強化
- 口腔筋機能のトレーニング:舌や咽頭の筋トレ習慣を導入し、睡眠中の気道閉塞を防止
さらに、市販のスリープポジショナー(体位保持器具)を試すことで、仰向け寝の習慣を無理なく変えることができます。これらの対策は医療機関との連携があってこそ安全に実施できるため、症状が重い場合は必ず専門医へご相談ください。
睡眠障害全般との関連と今後のケアのポイント
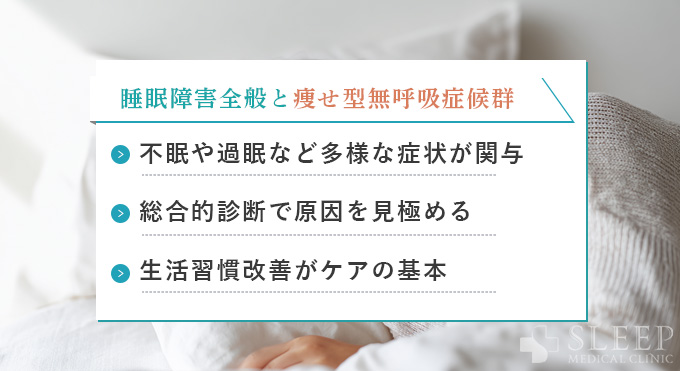
睡眠障害には様々な種類があり、その中で睡眠時無呼吸症候群が占める割合は大きいです。しかし痩せ型の方が抱える睡眠の問題は多様であり、無呼吸以外の睡眠障害との境界は必ずしも明確ではありません。ここでは睡眠障害の概念を広げ、どのように総合的なケアを行うべきかご案内します。
睡眠障害とは何か、その種類と症状
睡眠障害は、睡眠の質や量に異常が起きる状態を指し、無呼吸症候群以外にも以下のようなタイプがあります。
- 不眠症:眠れない、眠りが浅いといった症状
- 過眠症:昼間の過剰な眠気や突然の眠り込み
- 概日リズム睡眠障害:体内時計の乱れによる睡眠時間の不規則性
- レストレスレッグス症候群:睡眠中や就寝前の足の不快感・運動欲求
痩せ型の方では、睡眠の浅さや中途覚醒が多く報告されており、無呼吸以外の要因が絡むこともあります。例えばストレス由来の不眠症が長引くと、無呼吸症状が悪化することも否定できません。
無呼吸症候群とその他睡眠障害の違い
無呼吸症候群は、気道の閉塞によって呼吸が繰り返し停止することで、睡眠の質が著しく低下し、結果的に日中の眠気や集中力低下をもたらします。一方、他の睡眠障害は呼吸とは直接関係がないことが多いですが、いずれも睡眠の質に悪影響を与えます。
診断的には終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)で無呼吸の有無を判定し、睡眠障害全般の診断では問診や睡眠日誌、場合によっては精神的な評価も加味します。このため、痩せ型の患者様が睡眠の悩みを複数抱えている場合は、総合的な専門的診断が重要です。
痩せ型の患者様の生活習慣見直しガイド
睡眠の質を高め、無呼吸症候群やその他の睡眠障害を予防・改善するには、日常生活の習慣改善が不可欠です。特に以下のポイントが痩せ型の方に推奨されます。
- 規則正しい睡眠時間の確保:就寝・起床時間を一定に保ち、体内時計を整える
- 適度な軽運動:ウォーキングやストレッチで身体をリラックスさせる
- 電子機器の使用制限:寝る1時間前はスマホやパソコンを避け、脳を休める
- ストレスマネジメント:瞑想や深呼吸、趣味などで心身のバランスを保つ
- 食事の見直し:就寝直前の重い食事を避け、消化に良い食事を心掛ける
こうした習慣改善は単独で劇的な矯正効果は期待しにくいものの、長期的には無呼吸の症状悪化を防ぎ、健やかな睡眠環境を整える基礎となります。
専門機関の活用と定期検査の重要性
痩せ型無呼吸症候群は見過ごされやすいため、症状を自覚したら早めに睡眠専門医の診察を受けることが重要です。専門医は多角的な検査から総合的な診断を下し、最適な治療法を提案してくれます。
定期的なフォローアップ検査は、治療効果の確認や症状の進行予防に欠かせません。特に手術後や機器療法中の患者様は、症状の変化や副作用の有無を詳細にチェックしてもらうことが推奨されます。
また、睡眠障害に精通したクリニックでは、行動療法やカウンセリングなども行っており、総合的な睡眠衛生の改善が可能です。痩せ型の患者様でも無呼吸以外の睡眠問題を併発している場合は、こうした包括的ケアが効果的です。

専門医の指導の下、機器療法や手術、生活習慣改善を組み合わせることが、長期的な睡眠の質向上につながります。こうした多面的なケアは、痩せ型でも無呼吸症候群によるリスクを最小限に抑えるために必須と言えるでしょう。
痩せ型無呼吸症候群にお悩みの方へ|スリープメディカルクリニックのご案内

当院「スリープメディカルクリニック」は、いびき・無呼吸の専門医療機関です。
私たちは単にいびきを治すだけでなく、患者様一人ひとりの「生活の質(QOL)」を高めることを理念に掲げ、最新の睡眠医学に基づくオーダーメイド治療を提供しています。
当院で導入している「スノアレーズ」は、痩せ型の方にも適応しやすいレーザー治療です。喉の組織を引き締めることで気道を拡げ、切らずに改善を目指せるため、骨格由来の気道狭窄にも有効です。施術は15分程度で、ダウンタイムも少なく、忙しい方にもご利用いただいております。
拠点は全国主要都市に展開しており、新宿・銀座・大阪・名古屋・福岡など駅近のクリニックがあり、WEB予約にも対応しております。
「自分はいびきや無呼吸とは無縁だと思っていた」「痩せているから心配ないと思っていた」という方こそ、ぜひ一度ご相談ください。私たち専門スタッフが、丁寧にお話を伺い、最適な治療プランをご提案いたします。
まずはオンライン予約にて、無料カウンセリングをお気軽にお申し込みください。痩せ型無呼吸症候群の不安や疑問を、ぜひスリープメディカルクリニックにご相談ください。
まとめ|痩せ型無呼吸症候群を正しく理解する
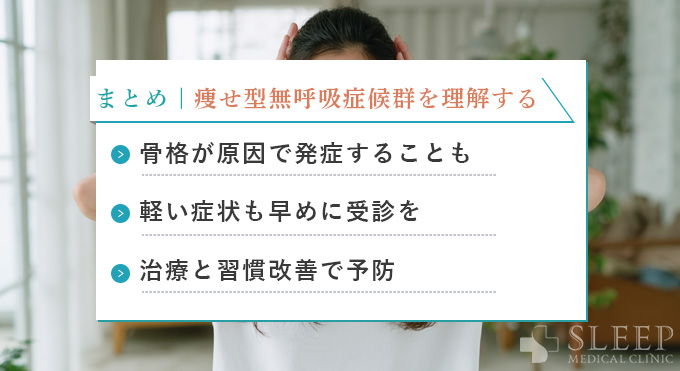
ここまで、痩せ型無呼吸症候群のリスクや症状、顎の骨格との関係、さらに有効な治療法について専門的視点から詳しく解説しました。痩せ型の方でも睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性が高く、肥満型とはまた異なるリスク因子が存在するということが確認できました。正しい知識を持つことで、早期発見・早期治療が可能となり、健康的な睡眠生活の維持につながります。
この記事のポイントおさらい
まず第一に、無呼吸症候群は単なる肥満者の病気ではありません。痩せ型の方には顎の骨格異常や気道の狭窄といった特徴的なリスク因子があり、それが気道閉塞を引き起こす大きな要因となっています。これらの骨格的な問題は、遺伝的要素や生まれつきの構造によることも多いため、体重が軽いからといって安心できません。
次に、症状の見分け方に注意が必要です。痩せ型の方は肥満型と違い、典型的な外見的サインが目立たないことから症状の見落としが起こりやすいです。いびきだけでなく、日中の強い眠気や集中力低下、頭痛などの軽微なサインも見逃さず、専門医による診断を受けることが大切です。
さらに、治療法も痩せ型ならではの特性に合わせた選択が重要です。一般的な生活習慣改善といった方法だけでなく、顎矯正を含む手術療法や、CPAP(持続陽圧呼吸療法)機器の使用が効果的なケースが多く報告されています。早期診断のうえで適切な治療を開始することで、症状の改善や合併症の予防が期待できます。
痩せ型でも深刻なリスクを防ぐためにできること
痩せ型の方々が睡眠時無呼吸症候群のリスクを抑えるために、日常生活でできる取り組みは多岐にわたります。まずは自己チェックを習慣にすることが大切です。いびきや呼吸停止、朝のだるさ、日中の眠気など、気になる症状に気づいたら放置せず、速やかに専門医に相談しましょう。
専門的な評価を受けることも不可欠です。耳鼻咽喉科や睡眠専門クリニックでの精密検査により、顎の骨格や気道の状態を詳細に把握できます。痩せ型特有のリスク要因を見落とさず診断を進めるために、検査項目をしっかり確認しましょう。
生活習慣面での改善も有効です。例えば、就寝時の姿勢を仰向けから横向きに変えることで、気道の閉塞を減らす効果が期待できます。また、規則正しい睡眠スケジュールや適度な運動、アルコール控えめな生活も快眠をサポートします。ただし、痩せ型の無呼吸症候群の場合は、特に骨格的要因のケアが重要になるため、医師の指示に従い専門的な治療を併用することが望ましいでしょう。
よくある質問
Q1: 痩せ型でも無呼吸症候群になるのはなぜですか?
A1: 体重ではなく、顎の骨格異常や気道の狭小化といった構造的な問題が主な原因です。痩せていてもこれらの条件が揃うと無呼吸症候群が発症します。
Q2: 痩せ型無呼吸症候群の治療はどのように選べば良いですか?
A2: 診断結果や症状の程度によりますが、CPAP療法、手術療法、生活習慣の見直しなどを組み合わせて実施します。専門医と相談し、個別に最適な治療計画を立てることが重要です。
Q3: いびきは必ず無呼吸症候群のサインですか?
A3: いびきは無呼吸症候群の代表的な症状ですが、いびきをかいても無呼吸症候群でない場合もあります。逆に痩せ型では軽いいびきでも無呼吸症候群が隠れていることがあるため、様々な症状を総合的に評価する必要があります。
Q4: 自宅でできる予防法はありますか?
A4: 横向きで寝る、就寝前の飲酒を控える、規則正しい睡眠習慣をつくることが基本ですが、痩せ型無呼吸症候群の場合は医療機関での診断・治療が第一優先です。
快適な睡眠は健康な生活の土台です。無呼吸症候群は決して見過ごしてはならない疾患であり、正しい知識をもとに早めの対応が何より大切です。違和感や不安を感じたらすぐに専門機関へ相談し、的確な診断と治療を受けて、質の高い睡眠と心身の健康を取り戻しましょう。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。