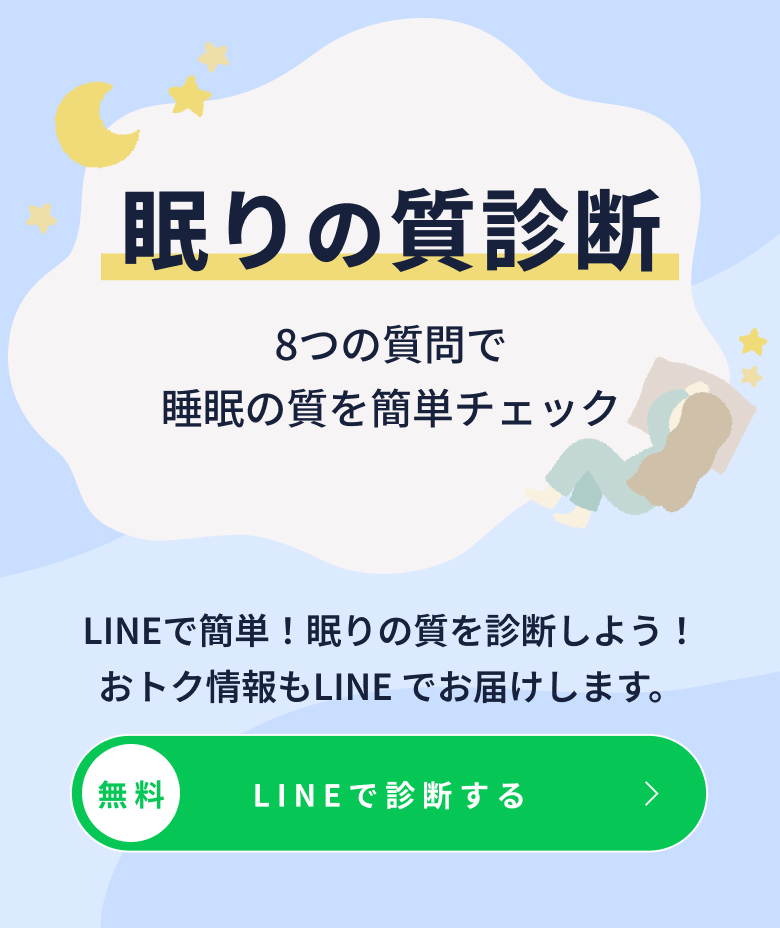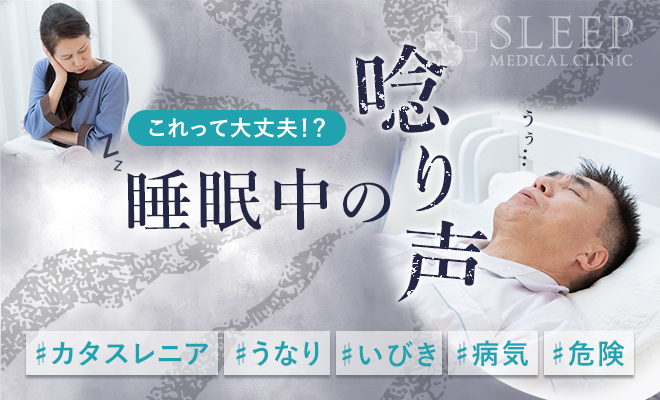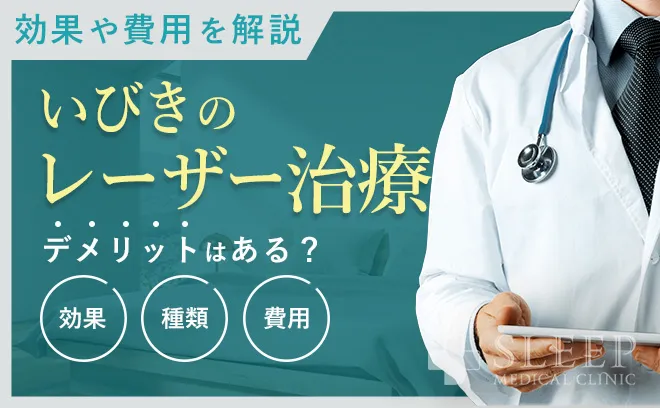睡眠時の口呼吸を治す方法|健康リスクを減らす具体的トレーニング完全ガイド
「夜、なんとなく口が乾いている」「睡眠中に自分が口呼吸をしているかもしれない」と感じたことはありませんか?睡眠時の口呼吸は意外と気づきにくいものですが、放置すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。多くの方が毎晩の呼吸に鼻ではなく口を使っており、その習慣が睡眠の質や体調不良に深く関係していることが近年の研究で明らかになっています。
睡眠時の口呼吸は、風邪や虫歯のリスクを高めるだけでなく、慢性的な鼻づまりやイビキ、さらには睡眠時無呼吸症候群といった深刻な睡眠障害の一因となることもあります。こうした健康リスクをできるだけ減らすためには、正しい知識を持ち、効果的な改善方法を実践することが欠かせません。実際に改善に成功した体験談や具体的なトレーニング法を知ることで、一歩踏み出す勇気が湧くでしょう。
本記事では、睡眠時の口呼吸の原因や健康リスクをわかりやすく解説しながら、なぜ鼻呼吸に変えることが重要なのかも詳しくご紹介します。また、日常生活に取り入れやすい口呼吸のトレーニング法や習慣改善策、さらには睡眠時無呼吸症候群との関連性についても触れます。加えて、実際に口呼吸を改善した方々の体験談や役立つアイテムの情報もお伝えし、皆様の健康的な睡眠環境づくりに役立てていただける内容を網羅しています。
「睡眠時 口呼吸 治し方」といったキーワードを軸に、専門的な視点を交えつつ、実践的で分かりやすい情報をお届けします。健康被害を未然に防ぎ、快適な眠りを取り戻すために、一緒に改善の第一歩を始めてみましょう。
睡眠時の口呼吸とは?原因と健康リスクを理解する
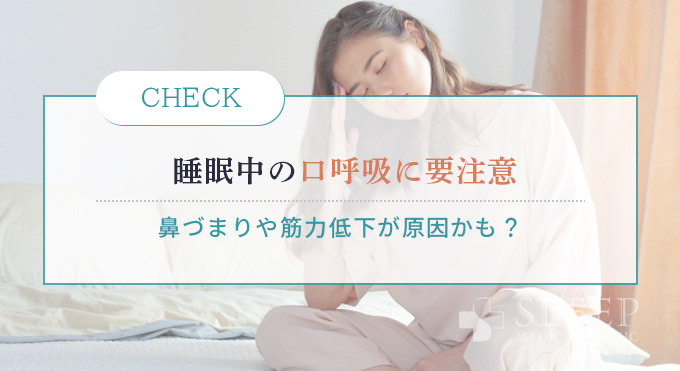
睡眠時の口呼吸は、無意識のうちに多くの方が経験している現象ですが、その影響は決して軽視できません。ここでは、口呼吸の仕組みや原因、そしてそれに伴う健康リスクを詳しく知ることで、自分の状態を正しく理解し、改善の必要性を感じていただくことを目的としています。
口呼吸のメカニズムと主な原因
口呼吸とは、本来鼻で行うべき呼吸を口で行ってしまう状態を指します。特に睡眠時に口が開いたままになり、空気が鼻を通らず口から直接肺へ入ることを言います。
口呼吸が起こるメカニズムにはいくつかの理由があります。まず、鼻の通りが悪いことが最も一般的な原因です。鼻づまりやアレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)などで鼻腔が狭くなると、鼻呼吸が困難になります。
また、口蓋垂(のどちんこ)の異常や、舌の位置の乱れ、口の周囲の筋肉の弱体化も口呼吸を促します。例えば、舌が下がった位置にあると喉の気道が狭くなり、呼吸しやすい口呼吸に頼るようになるのです。
子どもでは、指しゃぶりや口唇の筋力不足が口呼吸の原因となることもあります。加えて、加齢や肥満による筋肉の低下も大人の睡眠時口呼吸に影響します。

ここで重要なのは、口呼吸自体が原因となってさらなる呼吸障害や健康問題を引き起こす悪循環に陥ることです。まずは自身の口呼吸の原因を見極めることが改善の第一歩です。
睡眠時の口呼吸がもたらす健康リスク
睡眠時の口呼吸は単に口元が開いているだけの問題ではなく、全身の健康に深刻な影響を及ぼします。以下に代表的な健康リスクを挙げ、その詳細を解説します。
- 口腔内の乾燥と虫歯リスクの増加
口呼吸によって唾液の保護機能が低下し、口腔内が乾燥します。唾液は虫歯や歯周病の予防に重要な役割を果たしていますので、その減少は虫歯の増加に直結します。 - 睡眠の質低下と日中の疲労感
口呼吸では、空気の湿度や温度の調節がなされず、喉周辺に炎症が起こりやすくなります。これにより、いびきや睡眠障害を引き起こし、熟睡できず日中の集中力低下や疲労感の原因となります。 - 慢性鼻炎や副鼻腔炎の悪化
口呼吸を続けると鼻の機能が低下し、鼻の粘膜の防御機能も弱まります。結果として慢性鼻炎や副鼻腔炎が悪化し、さらに鼻呼吸が困難になるという悪循環が生じます。 - 姿勢の悪化や顎関節症のリスク
無意識の口呼吸は、頭や首の位置にも影響します。顎を突き出すような姿勢を取りやすくなり、顎関節症や首・肩の痛みが生じることがあります。 - 睡眠時無呼吸症候群の増悪
口呼吸は気道の閉塞を助長し、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を悪化させるリスクがあります。これは健康に極めて重大な影響を及ぼし、専門医の診察が必要です。
以上のように、口呼吸はさまざまな健康問題に結びつき、放置すると症状の悪化や生活の質低下につながります。専門的には、口呼吸がもたらす悪影響は今や重要な医療課題と位置付けられているのです。
睡眠と健康の関係については、厚生労働省の睡眠対策も参考にしてください。
睡眠時の口呼吸のセルフチェック
まず自分が睡眠時に口呼吸をしているかを知ることが改善への第一歩です。以下の簡単なセルフチェック法や周囲からの確認ポイントを参考にしてください。
- 翌朝の口や喉の乾燥・不快感
口が渇いたり、喉の痛み・違和感を感じる場合は睡眠時口呼吸の可能性が高いです。 - いびきや無呼吸の指摘
家族やパートナーからいびきを頻繁にかいている、呼吸が止まっていると指摘された場合は注意が必要です。なお、男女でのいびきの違いを知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。 - 日中の睡魔や集中力低下
睡眠の質が低下しているサインとして、日中に強い眠気や集中力不足を感じることがあります。 - 口の周りの筋力低下
鏡でリラックスした状態の口元を観察し、口が開いている・力が入りにくい場合も口呼吸傾向を示します。 - 鼻づまりや鼻炎の自覚
鼻が詰まりやすく、鼻呼吸がしづらい状態は口呼吸の大きな原因です。
客観的な判断には、睡眠中の録音や撮影、専門の睡眠検査(ポリソムノグラフィー)も有効です。特に健康リスクの疑いが強い場合は専門機関への相談をおすすめします。
日々のセルフチェックに加え、生活環境や症状の変化に敏感になることで、早期発見・改善につながります。口呼吸の改善は健康維持の重要な一歩です。
鼻呼吸のメリット|なぜ鼻呼吸に改善すべきか

鼻呼吸は健康的な呼吸法の基本であり、睡眠時の口呼吸を治す上で最も重要なポイントです。ここでは鼻呼吸がもたらす具体的な効果や、睡眠の質が向上する理由、さらに鼻呼吸を促進するための環境整備のコツを詳しく解説します。
鼻呼吸が体にもたらす具体的な効果
鼻呼吸は鼻腔を通して空気を取り込む呼吸方法で、体にさまざまな健康効果をもたらします。まず、鼻は吸い込む空気を温め、湿らせる役割を果たしています。この機能により乾燥した空気や異物の刺激から肺を守ることができます。
また、鼻の粘膜には微細な毛(繊毛)があり、チリやほこり、細菌を捕捉して身体への侵入を防ぎます。このフィルター機能によって、感染症リスクが低下し免疫がサポートされます。
さらに、鼻呼吸では一酸化窒素(NO)が鼻腔から肺に送られます。この物質は血管を広げ、血流を良くして酸素の運搬効率を高めます。結果として、心臓や脳への酸素供給が向上し、全身の代謝も活性化します。
さらに、鼻呼吸は横隔膜の動きを促進し、深くゆったりとした呼吸を可能にします。これは自律神経のバランスを整え、ストレス軽減やリラックス状態の維持に寄与します。
このように鼻呼吸は、身体の自然な防御機構を活かしながら、呼吸効率や健康状態を最適に保つために欠かせません。
鼻呼吸が睡眠の質を高める理由
鼻呼吸は眠っている間の呼吸の質を高め、睡眠全体の質向上に直結します。まず鼻呼吸をすることで、空気が適切に温められ湿度も補われるため、気道の粘膜が乾燥せず刺激を軽減します。
その結果、いびきの発生が抑制され、気道の通りが良くなることで無呼吸や呼吸の乱れを防止しやすくなります。呼吸が安定するため、中途覚醒の減少も期待できます。
さらに、鼻呼吸は副交感神経の働きを活性化しやすいため、入眠を促進して深い睡眠フェーズに入りやすくなります。この効果は日中の疲労感や注意力の低下を和らげ、健康的な生活リズムを支える鍵となります。
実際に睡眠時の鼻呼吸促進に取り組んだ方々からは、「翌朝の目覚めが良くなった」「日中の眠気が減った」といった体感報告が多く寄せられています。つまり、鼻呼吸は睡眠の質を根本から改善する有効な方法なのです。
鼻呼吸促進のための環境整備ポイント
鼻呼吸を習慣化するには、寝室や生活環境の整備も重要です。まず室内の空気を清潔に保つこと。ホコリや花粉、カビを減らすことで鼻の炎症やアレルギー症状を緩和しやすくなります。
適度な温度と湿度も心がけましょう。特に冬場の乾燥は鼻腔粘膜を傷つけ、鼻づまりを引き起こします。加湿器を使用し、湿度を50~60%程度に保つことが望ましいです。
睡眠時の姿勢も鼻呼吸を促します。仰向けは気道が狭くなるため、横向き寝が推奨されます。また、鼻詰まりがある場合は就寝前に鼻洗浄や点鼻薬を用いることで通りを改善できます。
さらに、ストレスや不規則な生活は自律神経の乱れを招きますので、規則正しい生活習慣を維持しリラックス環境を作ることも鼻呼吸にとって大切です。
これらの環境整備によって、鼻呼吸がしやすい身体と生活環境を整え、口呼吸習慣からの脱却を後押しします。継続的な取り組みが健康改善の鍵です。
睡眠時の口呼吸の治し方|トレーニングと習慣改善法
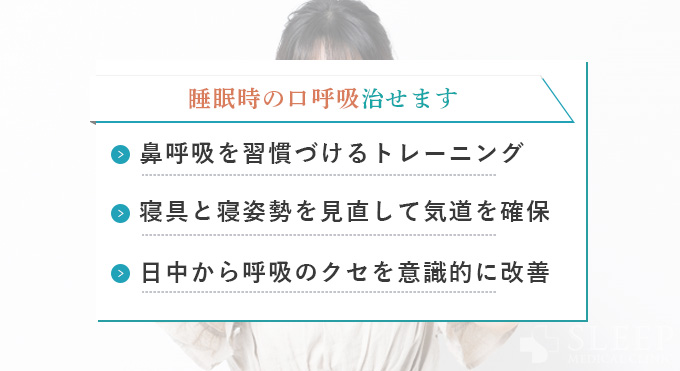
睡眠時の口呼吸を改善するためには、正しい呼吸習慣の形成に加え、口まわりの筋肉を強化し鼻呼吸を促進するトレーニングが重要です。ここでは専門的な呼吸筋トレーニングや生活習慣の見直し、さらには寝具や寝姿勢の工夫を具体的にご紹介します。日常生活に取り入れやすい方法を中心に、口呼吸改善への確かな一歩を踏み出しましょう。
口呼吸改善のための筋肉トレーニングメニュー
口呼吸の根本的な原因の一つは、口唇周辺や舌の筋力低下にあります。これらを鍛えることで自然と鼻呼吸を促しやすくなり、口呼吸の習慣を改善できます。特におすすめの筋肉トレーニングをいくつかご紹介します。
- 舌先の上あごタッピングトレーニング:
舌先を上あごに押し当てた状態で、ゆっくりとタッピングを繰り返します。1日に3セット、各セット15秒程度を目安に行うと舌筋の持久力がつき、気道の空間確保に役立ちます。 - 口唇閉鎖トレーニング:
唇を強く閉じて5秒間キープし、ゆっくりと緩める動作を20回繰り返します。習慣的に行うことで唇まわりの筋肉を強化し、自然な鼻呼吸に導きます。 - 頬筋の引き上げトレーニング:
頬を内側から指で軽く押さえて支えながら、頬の筋肉を意識的に引き上げて10秒キープ。これを1日3回行うと頬筋が強化され、口まわりの筋肉バランスが整います。
さらに、舌の位置を正しく保つことも重要です。日中から舌先を上あごの前歯のすぐ裏側に当てる意識を持つことで、舌の自然な位置と呼吸経路の改善につながります。
日中の呼吸習慣見直し
口呼吸は夜間だけでなく、日中の呼吸習慣とも深く結びついています。日中の習慣改善なくして、効果的な夜間の口呼吸改善は困難です。以下に段階的に取り組みやすいステップをまとめました。
- 意識的な鼻呼吸の実践:
歩行時や座っている時など、日常のあらゆる場面で「口を閉じて鼻呼吸」を意識することが最初の大切なポイントです。スマートフォンのリマインダー等を活用し、数分おきに確認すると効果的です。 - 呼吸リズムの整え方:
深呼吸や腹式呼吸の習慣を取り入れ、呼吸の浅さを改善します。特に、ゆっくりとした息吐きができるようになると気道が安定し、鼻呼吸の促進に繋がります。 - 口呼吸癖を招く環境の排除:
エアコンや暖房の乾燥、アレルギーを誘発するハウスダストなどは、鼻づまりを招きやすく口呼吸の原因になります。加湿器を用いる、定期的な掃除で環境を整えることが効果的です。

特にストレスが高い場合や緊張状態では呼吸が浅くなり、口呼吸に繋がりやすい傾向が見られます。瞑想やストレッチによるリラクゼーション法を取り入れて、自律神経のバランスを整えることも補助的な対策となるでしょう。
寝具や姿勢を工夫した改善策
睡眠中の口呼吸を予防するには、寝具や寝姿勢を適切に整えることも重要な要素です。気道の状態や体圧の分散が良くなることで、自然な鼻呼吸がしやすくなります。
- 高さ調整可能な枕の使用:
首や頭の位置を適切に保つことで、気道が閉塞されにくくなり、呼吸がスムーズに進みます。高すぎる枕は逆に首を圧迫するため、寝返りしやすい硬さとサイズ選びがカギです。 - 仰向け寝改善の姿勢変更:
横向き寝も気道を解放しやすいですが、横向き寝用サポートクッションを使用すると安定しやすく、口呼吸の抑制につながります。特に左側を下にすると心臓負担を軽減しつつ呼吸も改善されるケースが報告されています。 - マウスピース型口閉じサポーターの活用:
就寝中に口が自然に開くのを防ぐための専用グッズもあります。医療機関推奨の製品を選び、装着感の調整ができるものを使用すると負担を軽減しつつ効果を得やすいです。
これらの寝具や姿勢の工夫は、単独でなく筋力トレーニングと併用することで寝ている間の口呼吸を効果的に減らすことに役立ちます。
睡眠時無呼吸症候群との関連性とその対策
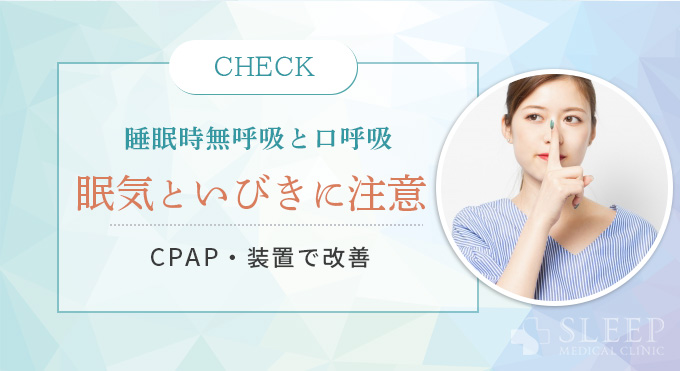
睡眠時の口呼吸は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)とも密接な関係があります。無呼吸症候群は重大な健康リスクを伴うため、早期の症状把握と対応が不可欠です。ここでは両者の関係、診断のポイント、効果的な対策法を具体的に解説します。
口呼吸と睡眠時無呼吸症候群の関係性
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に気道が一時的に閉塞し、呼吸が止まったり浅くなったりする状態を指します。口呼吸は鼻腔の機能が低下していることが多く、気道閉塞のリスクを高める要因の一つです。
無呼吸症候群の代表的な症状には、いびきの激化、日中の強い眠気、集中力の低下、高血圧の進行などがあります。これらは口呼吸の悪化と相まって、心血管疾患や糖尿病の発症リスクも増加すると指摘されています。
また、睡眠中に口が開いている状態は乾燥を招き、気道粘膜の防御機能を低下させることで炎症やむずむず感が生じやすいのも特徴です。このため無呼吸症候群への進展を加速させる場合もあるため、注意が必要です。
無呼吸症候群の症状には、いびきや日中の眠気などがあります。詳しくは「睡眠時無呼吸症候群の症状とは?セルフチェックや検査の方法」をご確認ください。
治療法と専門医への相談タイミング
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、早めに専門医を受診することが推奨されます。特に、日中の過度な眠気や記憶障害、判定テストで高スコアを取った場合は速やかな検査が必要です。
- ポリソムノグラフィー検査(PSG):
睡眠中の呼吸状態を詳細に測定する検査で、無呼吸の有無と重症度を判定します。 - CPAP療法(持続陽圧呼吸療法):
最も一般的な無呼吸症候群の治療法で、就寝中にマスクを装着し気道を圧迫して閉塞を防ぎます。 - 口腔内装置:
口呼吸に関連した軽度の無呼吸症候群の場合、顎や舌の位置を調整するマウスピースタイプの装置も効果的です。
加えて、体重管理や禁煙、アルコール制限といった生活習慣の改善も治療の要となります。これらの措置は気道を狭くする要因減少に貢献し、口呼吸の負のスパイラルを断ち切る効果があります。
診断ドリルと入眠前のセルフケア法
自宅でできる簡易診断として、以下のチェックリストを活用することで早期に異常を察知しやすくなります。
- 夜間に大きないびきをかいていると指摘されたことがある
- 日中に強い眠気を感じることが頻繁にある
- 起床時に喉の渇きや口の乾燥がひどい
- 集中力の低下や記憶力減退を感じる
- 家族から呼吸が止まっている様子を観察された
これらに当てはまる場合は、専門機関での診断を早めに受けることが大切です。
また、入眠前のセルフケアとしては、寝る1〜2時間前に軽いストレッチや深呼吸練習をおこないリラックスした状態で就寝することが効果的です。鼻腔洗浄や蒸気吸入で鼻づまりを解消し、可能な限り鼻呼吸しやすい環境を整えましょう。
口呼吸の改善に成功した体験談とおすすめグッズ・サポート
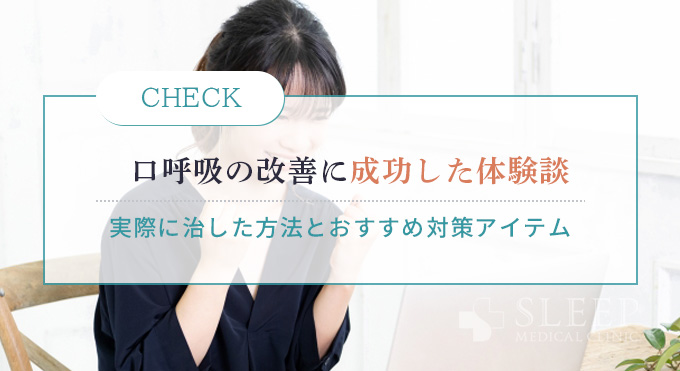
実際に口呼吸の改善に成功した方々の体験談は、取り組みを始めるきっかけやモチベーションとなります。加えて、多様なサポートグッズの選び方も重要なポイント。ここでは生の声と使って効果を実感したアイテムを紹介し、より具体的なイメージ形成を支援します。
実際に治した人の体験談から学ぶポイント
30代女性のA様は、慢性的な口呼吸による喉の乾燥と疲労感で悩んでいました。舌の筋トレを日々続けつつ、寝具の高さ調整や横向き寝に変更することで1ヶ月ほどで呼吸の質が改善。体のだるさが減り、集中力も回復したといいます。
一方、50代男性のB様は睡眠時無呼吸症候群を伴う強い口呼吸で寝不足状態が続き、専門クリニックでCPAP療法を開始。加えて口を閉じるマウスピースも取り入れ、症状が劇的に改善。現在では日中の眠気も解消され、家族からのいびき指摘もなくなったそうです。
これらの体験からわかることは、筋トレや環境改善だけでなく、場合によっては専門的医療機関の相談が早期改善に不可欠であるということです。自分に合った方法を見つけるための試行錯誤も重要です。
効果が期待できるグッズ・アイテムの特徴比較
- 口閉じテープ:
就寝時に唇をテープで固定し、自然な鼻呼吸を促進。手軽でコストが低い反面、肌荒れを起こしやすい人もいるため注意が必要。 - マウスピース型口閉じサポーター:
口の開きを物理的に防止し、CPAP治療との併用も可能。装着感や馴染みは個人差が大きいため、試着や医師のアドバイスが望ましい。 - 鼻腔拡張器:
鼻の通りを確保する器具で、鼻呼吸をしやすくする効果がある。就寝時以外にも日中の鼻づまり緩和として使用できる。 - 加湿器・空気清浄機:
室内環境を整え鼻詰まりの緩和を目指すアイテム。特に乾燥しやすい季節には必須で、鼻呼吸促進と睡眠の質向上が期待できる。
これらのグッズは、実際に用いる際は自分の体質や使用感を優先し、過度な使用は避けることが大切です。医療機関の推奨品や専門スタッフの相談を活用することも安心材料となります。
専門家が推奨するサポートサービス紹介
近年、睡眠専門クリニックや呼吸療法の専門家が監修するトレーニングプログラムが増加しています。例えばリモートで口呼吸トレーニング指導を受けられるオンラインサービスや、自宅で使える専用機器を組み合わせたケアが注目されています。
こうしたサービスは、個別の症状に合わせた継続的なフォローアップやモチベーション維持に優れている点が魅力です。また、医療機関と連携して体の状態に基づくアドバイスを受けられるため、自己流よりも効果が高い傾向にあります。
全国には専門医と連携した睡眠改善クリニックも多数あり、口呼吸改善に特化した診療やトレーニング指導が提供されています。疑わしい症状がある場合や慢性的な口呼吸にお困りの方は、専門医への相談を積極的に検討しましょう。
総じて、口呼吸改善は一朝一夕ではなく、筋肉トレーニング・生活習慣の見直し・医療的ケアの三本柱をバランスよく取り入れることが成功の鍵となります。
いびき治療なら「スリープメディカルクリニック」へ
.jpg)
いびき改善の治療法を探している方に、スリープメディカルクリニックのレーザー治療が注目されています。当院では、いびき専用のレーザー機器「スノアレーズ」を用いた治療法を採用しており、短時間かつ負担の少ない施術で効果が期待できるのが特長です。
また、CPAP療法も、重度のいびきや睡眠時無呼吸症候群の治療に有効です。睡眠中に気道を常に開いた状態に保つことで、いびきや無呼吸の症状を軽減します。医師による適切な診断のもと、患者様の状態に合わせてCPAP機器を選定・指導いたします。
当院では保険適用の治療は行っておりませんが、その分、自由診療だからこそ提供できる最先端のアプローチと個別対応にこだわっています。
詳しくは、当院のいびき治療についてもご覧ください。ご予約はオンラインにて24時間受付中です。
まとめ|睡眠時口呼吸の治し方のポイント
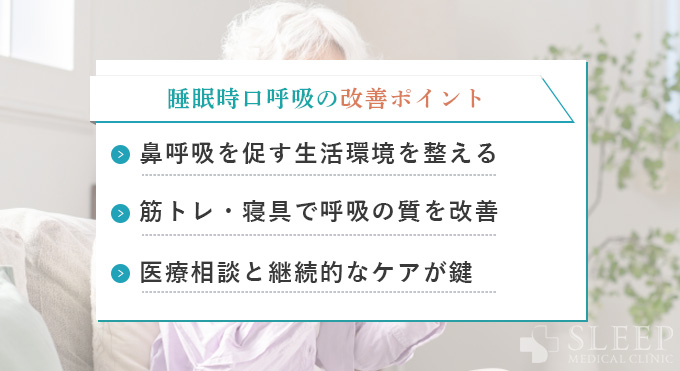
睡眠時の口呼吸は、健康に多大な影響を及ぼすため、早期の改善と継続的なケアが欠かせません。ここでは、これまでご紹介した知識や対策を振り返りつつ、長期的に健康を守るために何をすべきかを整理します。口呼吸の治し方は一過性のものではなく、生活習慣の見直しと習慣化が不可欠であることを改めて理解しましょう。
治療法の振り返りと長期的なケアの重要性
口呼吸の原因は多岐にわたり、鼻づまりや筋力低下、姿勢の悪さなど複数の要素が絡み合っています。したがって、その治療法も多角的なアプローチが必要です。具体的には、鼻呼吸のメリットを意識して鼻の通りを良くする環境づくりや、口周りの筋肉トレーニングによる筋力強化、日中の呼吸習慣の見直しが基本です。
さらに、睡眠時無呼吸症候群などの合併症リスクを軽減するためには、専門医による診断相談も有効です。初期のセルフチェックで異変を感じた場合は、早期に医療機関を訪れることが大切です。治療後も継続的に口呼吸が再発しないよう、長期的観点でのケアや生活習慣の改善が求められます。
長期的ケアとしては、日々の呼吸意識を高め、鼻呼吸を促す生活環境の維持、適切な寝具や寝姿勢の工夫が役立ちます。加えて、定期的な筋肉トレーニングを日課にし、口周辺の筋力を鍛えることも再発防止に効果的です。根気強く取り組むことが、口呼吸改善の鍵となるでしょう。
早期改善で得られる健康メリット
睡眠時の口呼吸を早期に改善すると、身体の様々な不調が緩和します。例えば、虫歯や歯周病といった口腔内のトラブルが減少し、口の乾燥による不快感が解消されます。呼吸がスムーズになることで、睡眠時無呼吸症候群のリスクも軽減され、睡眠の質が向上することが期待されます。
また、鼻呼吸は空気の加湿や温度調節、ウイルスや細菌の侵入防止など、身体の自然免疫機能をサポートします。これにより風邪やアレルギー症状の緩和にもつながり、日中の疲労感や集中力の低下も改善できるのです。健康面だけでなく、全体的な生活の質の向上にも寄与します。
生活リズムの乱れやストレスの軽減にも鼻呼吸は有効であり、精神的な安定にもつながるため、幅広い健康メリットが得られます。口呼吸を早めに正すことは、将来的な健康トラブルの予防という大きな効果をもたらします。
最新の研究・情報の入手方法
呼吸や睡眠に関する医療・科学の分野は日々進歩しており、新たな治療法や改善方法が報告されています。ご自身やご家族の健康管理のため、最新情報を定期的にチェックする習慣をつけることが重要です。
信頼できる情報源としては、厚生労働省や日本睡眠学会、呼吸器専門医会などの公式サイトが挙げられます。これらの機関は最新の研究成果や治療ガイドライン、予防策を公表しているため、正確な知識の入手に役立ちます。
また、いびきや睡眠時無呼吸症候群の専門クリニックが発信する情報や、専門医監修の書籍・セミナーも有用です。日々の生活に取り入れやすい呼吸トレーニングや生活習慣の具体例も積極的に紹介されており、取り組みやすい内容となっています。
健康維持のためには、新しい情報にアンテナを張り、変化に柔軟に対応することが求められます。定期的にチェックし信頼できる情報を得ることで、より効果的な口呼吸改善や睡眠の質向上を目指すことができるでしょう。

大阪大学医学部を卒業後、大学病院や一般病院での臨床経験を経てレーザー治療を中心に専門性を磨き、日本レーザー医学会認定医1種や日本抗加齢医学会専門医の資格を取得。その豊富な実績が評価され、某大手クリニックで総院長を務めるなど、10年以上にわたり医療の最前線で活躍しています。また、著書『医師が教える最強のメンズ美容ハック』(幻冬舎)などを通じて、レーザー治療や健康管理に関する情報を積極的に発信。現在は、その長年の知見と技術力を活かし、いびきのレーザー治療クリニックを監修し、患者一人ひとりの悩みに寄り添った安全かつ効果的な治療を提供しています。